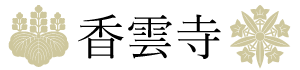命日から49日までの「中陰」と呼ばれる期間は、故人の魂がさまよっているとされています。
故人の魂が安らかに成仏することを目的として行われるのが、忌日法要です。
大切な方が亡くなった際に安心して法事ができるよう、どのような時期に行うべきかを紹介します。
▼忌日法要が行われる時期
仏教では、亡くなった人の行くべき場所を決める裁判が、7日ごとに行われるとされています。
このことから、忌日法要は命日から7日ごとの時期に実施されることがほとんどです。
場合によっては、親族のみで簡易的に行ったり省略したりすることもありますが、大切にすべき忌日法要が2つあります。
■7日目
亡くなってから行われる最初の忌日法要で、初七日とも呼ばれます。
僧侶による読経や焼香・精進落としの会食などが行われ、命日を含めた7日目に実施されることがほとんどです。
親族や知人などが参加しますが、7日目に再度集まることが難しい場合は、火葬後に行うこともあります。
■49日目
七七日忌とも呼ばれ、命日から49日目に行われる最後の忌日法要です。
実際は49日目より早めの時期が選ばれることが多く、参加する方が集まりやすいタイミングで行われます。
初七日と同じような参加者・スケジュールですが、一緒に納骨も行われる場合が多いことも特徴です。
▼まとめ
忌日法要が行われる時期は、亡くなった日から7日ごとです。
時期によって省略されることもありますが、最初の7日目と最後の49日目は大切なタイミングですので、法要を行い故人を送り出しましょう。
佐賀の『宗教法人香雲寺』では、お葬式や法事などさまざまな儀式のお手伝いをしております。
地域に寄り添い、心を込めて対応いたしますので、お困りの際はご相談ください。